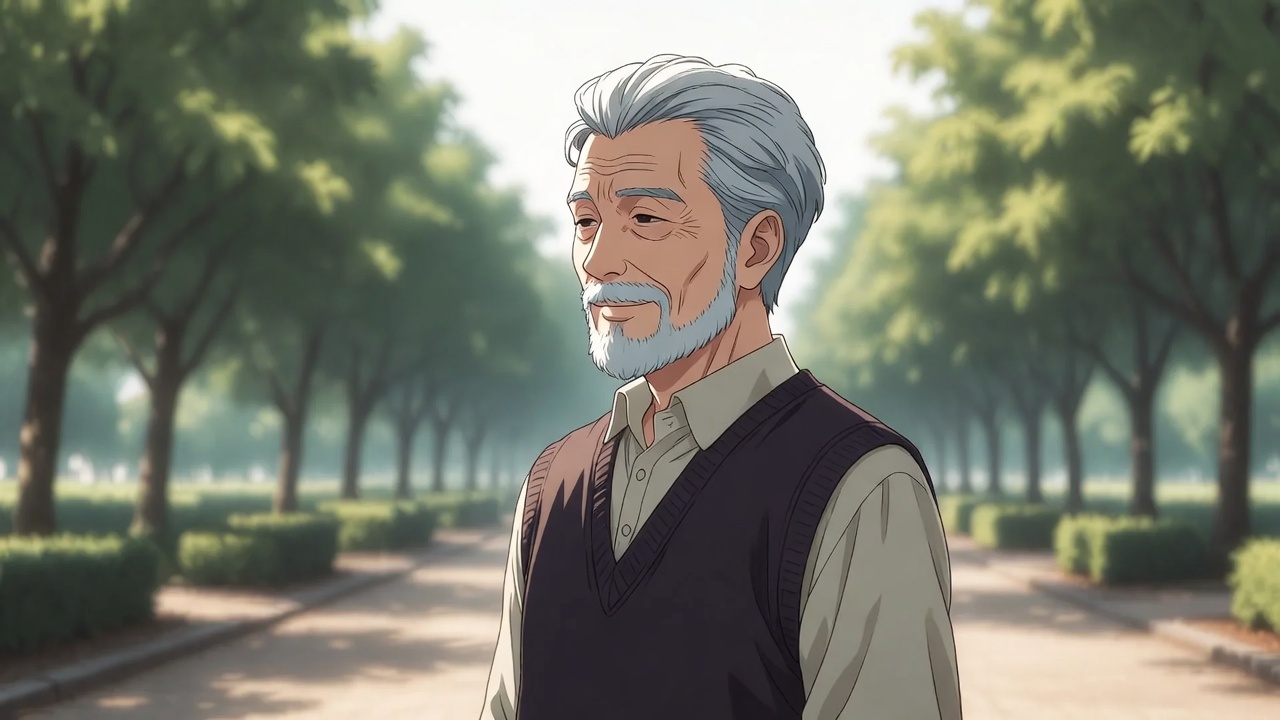猫でも書ける短編小説
◀第1章 雨の日の出会い
▶第9章 空の下の沈黙
「VOICEVOX: 四国めたん」「VOICEVOX: 冥鳴ひまり」「VOICEVOX: 離途」「VOICEVOX: 玄野武宏」
|
第5章 見つかった秘密
春の風が、少しずつ暖かくなってきた。
公園の桜はまだ蕾のままだけれど、空の色は冬よりも柔らかく、光が差し込む時間が長くなっていた。
私は、今日もココに会いに行く。
それが、私の日常になっていた。
ココは元気だった。
尻尾を振って、私の足元に駆け寄ってくる。
パンを食べるときのくちゃくちゃという音も、耳に心地よく響く。
誰かと一緒にいることが、こんなにも安心できるなんて。
私は、ココと過ごす時間が、何よりも大切になっていた。
その日も、いつものように公園でココと遊んでいた。
ボールを投げると、ココは嬉しそうに走って取りに行く。
私は笑って、ココも笑っているように見えた。
でも、その笑顔が突然止まった。
「遥?」
振り返ると、母が立っていた。
仕事帰りなのか、スーツ姿で、手には買い物袋を持っていた。
その目が、私とココを見て、驚きと困惑で揺れていた。

「……その犬、どうしたの?」
私は、言葉が出なかった。
ずっと隠していたことが、突然目の前に現れてしまった。
ココは、母の顔を見て、少しだけ尻尾を振った。
でも、母は動かなかった。
「ダメでしょ。ちゃんと責任を取れないなら関われない」
その言葉が、胸に突き刺さった。
私は、ココを見て、そして母を見た。
何かを言わなきゃと思ったけれど、言葉が出なかった。
「……でも、この子がいないと、私……寂しい」
ようやく絞り出した言葉は、涙と一緒にこぼれた。
母は、少しだけ目を見開いて、黙ったままだった。
「ずっとひとりだった。家でも、学校でも。
でも、ココがいてくれて、初めて……誰かと繋がれた気がしたの。
この子がいないと、また、ひとりぼっちになる」
涙が止まらなかった。
ココは、私の足元に寄り添って、静かに座っていた。
その姿が、私を守ってくれているようで、余計に涙が溢れた。
母は、しばらく黙っていた。
そして、ゆっくりとしゃがみ込んで、ココの顔を見た。
「……名前は?」
「ココ。“ここにいてほしい”って意味で」
母は、小さく息を吐いて、立ち上がった。
「家には連れて帰れない。仕事もあるし、世話もできない。
でも……」
その言葉の続きを、私は待った。
心臓がどくどくと鳴っていた。
「……一度、ちゃんと考える。その代わり、責任は持つこと。
ごはん、散歩、病院。全部、ちゃんとやるって約束できる?」
私は、何度も頷いた。
涙でぐしゃぐしゃになりながら、「うん」と言った。
その夜、家に帰っても、母は何も言わなかった。
でも、私の部屋の前に、小さなタオルと空の容器が置かれていた。
それが、母からの答えのように思えた。
翌日、公園で老人に会った。
いつものように掃除をしていたその人は、私とココを見て、にこりと笑った。
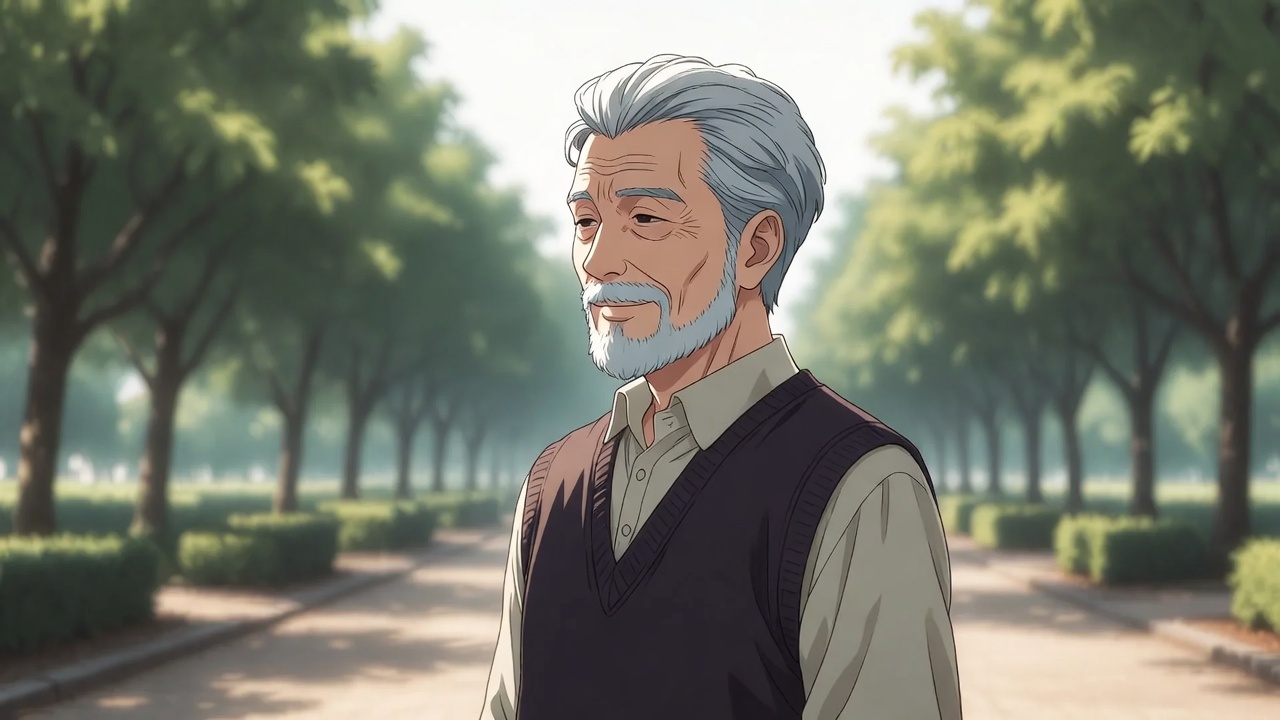
「お母さんに見つかったか」
「……はい。でも、少しだけ、わかってくれたみたいです」
老人は、ココの頭を撫でながら言った。
「人は、誰かを守りたいと思ったとき、強くなれる。
君は、ココを守りたいと思った。
それが、きっとお母さんにも伝わったんだろう」
その言葉が、胸にじんと響いた。
私は、ココの頭を撫でながら、そっと呟いた。
「ありがとう、ココ。私、ちゃんと守るからね」
ココは、静かに尻尾を振った。
その動きが、私の心に優しく響いた。
そして私は、初めて「家族」という言葉を、少しだけ信じてみようと思った。
|
第6章 あたたかな冬
冬の朝は、空気が澄んでいて、音が遠くに感じる。
窓の外に広がる白い息と、吐くたびに曇るガラス。
そんな季節が、私は少しだけ好きになった。
理由は、ココがそばにいるから。
あの日、公園で母に見つかってから、ココは家に来ることになった。
「責任を持つなら」という条件付きだったけれど、私にとっては夢のような出来事だった。
玄関にココのためのタオルを敷いて、空の容器に水を入れて。
それだけで、家の空気が少しだけ柔らかくなった気がした。
母は相変わらず忙しくて、会話は多くない。
でも、ココのことになると、少しだけ立ち止まってくれる。
「ごはん、ちゃんとあげた?」
「散歩は行ったの?」
そんな言葉が、私には嬉しかった。
ココは、家の中でも静かだった。
吠えることはほとんどなくて、私の後をちょこちょことついてくる。
私が勉強していると、足元で丸くなって眠る。
その寝息が、部屋の静けさを優しく包んでくれる。
ある日、学校から帰ると、母がリビングにいた。
珍しく早く帰ってきたらしく、テーブルの上には小さな箱が置かれていた。
「誕生日、おめでとう」
母がそう言った瞬間、私は一瞬言葉を失った。
誕生日を覚えていてくれたことが、驚きだった。
箱を開けると、中には赤い首輪が入っていた。
小さくて、柔らかい革でできた、ココにぴったりのサイズ。
「これで正式に、うちの子ね」
母の言葉に、胸がじんとした。
ココは、私の隣で尻尾を振っていた。
まるで、自分の名前を呼ばれたように。
私は、首輪をそっとココの首に巻いた。
ココは嫌がることもなく、むしろ誇らしげに見えた。
その姿を見て、母が少しだけ笑った。
「似合ってるね」
その言葉が、私の心に深く染み込んだ。
家族って、こういう瞬間の積み重ねなのかもしれない。
誰かが誰かを思って、何かを贈る。
それが、絆になる。
その夜、私は日記を書いた。
「今日、ココに首輪をつけた。
母がくれた。
“うちの子”って言ってくれた。
ココが家族になった日。
私の誕生日が、初めて嬉しかった。」
ページを閉じると、涙が少しだけこぼれた。
でも、それは悲しさじゃなくて、あたたかさの涙だった。
冬の夜は冷えるけれど、ストーブの前はぽかぽかしている。
私は毛布を広げて、ココと並んで座った。
ココは、私の膝に顔を乗せて、目を閉じた。
その寝顔が、何よりのプレゼントだった。
母がキッチンで何かを温めている音が、遠くで聞こえる。
その音も、今は心地よく感じる。
家の中に、誰かがいる。
それだけで、安心できる。
私は、ココの頭を撫でながら、そっと呟いた。
「ありがとう、ココ。
私、少しずつ変われてる気がするよ」
ココは、寝たまま尻尾をふりふりと動かした。
その動きが、私の言葉に応えてくれているようで、胸があたたかくなった。
窓の外には、雪がちらちらと舞っていた。
静かな夜。
でも、心の中には、確かな灯りがともっていた。
そして私は、明日もまた、ココと一緒に過ごせることを願いながら、眠りについた。
|
第7章 春の異変
春が来た。
窓を開けると、風がやわらかく頬を撫でていく。
庭の隅に植えられたチューリップが、つぼみを膨らませていた。
空は高く、雲は薄く、世界が少しずつ色づいていく。
でも、私の心は、なぜか晴れなかった。
ココの様子が、少しずつ変わってきた。
朝、起きるのが遅くなった。
ごはんを出しても、前みたいに飛びついてこない。
散歩に誘っても、玄関で立ち止まることが増えた。
「ココ、どうしたの?」
何度も声をかけた。
頭を撫でても、尻尾はゆっくりとしか動かない。
それでも、私の顔を見て、静かに寄り添ってくれる。
その優しさが、逆に不安を大きくした。
母に相談すると、すぐに動物病院に連れて行こうと言ってくれた。
車に乗って、ココを膝に抱えながら、私はずっと胸がざわざわしていた。
病院の待合室で、他の犬たちの元気な声が響く中、ココは静かに私の腕の中にいた。
診察室で、獣医さんがココを優しく撫でながら言った。
「老犬ですね。年齢的にも、そろそろ体に負担が出てくる頃です。
食欲の低下やふらつきは、老化のサインかもしれません。
……もう長くはないかもしれません」
その言葉が、頭の中で何度も繰り返された。
「長くはない」
「老犬」
「負担」
私は、何も言えなかった。
ココの背中を撫でながら、ただ涙がこぼれていった。
帰り道、車の窓から見える桜の並木が、満開に近づいていた。
ピンク色の花びらが風に舞って、道を染めていた。
でも、その美しさが、今は苦しかった。
「春は嫌いになりそう」
私は、そう呟いた。
ココは、私の膝の上で目を閉じていた。
その寝顔が、あまりにも静かで、あまりにも優しくて。
私は、どうしても現実を受け入れられなかった。
家に帰ってからも、私はずっとココのそばにいた。
ごはんを食べない日は、スープを作ってスプーンで口元に運んだ。
散歩に行けない日は、庭に出て、日向ぼっこをした。
それでも、ココは少しずつ、静かになっていった。
日記には、こんな言葉を書いた。
「ココが、あまり食べなくなった。
病院で、老犬だって言われた。
そんなはずない。
ココは、ずっと元気でいてくれると思ってた。
でも、春が来るたびに、心がざわざわする。
花が咲くのに、私は泣きそうになる。」
ページを閉じると、涙がぽろぽろと落ちた。
ココの寝息が、隣で静かに響いていた。
その音が、私を現実に引き戻す。
母は、何も言わずにそっと毛布をかけてくれた。
その手の温かさが、少しだけ私を支えてくれた。
「ココ……お願い、もう少しだけ、そばにいて」
私は、そう願った。
春の風が、窓の隙間からそっと吹き込んできた。
その風が、ココの毛を揺らした。
そして私は、春が怖くなった。
|
第8章 最後の散歩
春の陽射しが、窓辺にやわらかく差し込んでいた。
部屋の空気は穏やかで、ストーブの温もりがまだ少し残っている。
私は、ココの寝顔を見つめながら、そっと息を吐いた。
ココは、もうほとんど歩けなくなっていた。
ごはんも、ほんの少ししか食べられない。
水を飲むのも、私がスプーンで口元に運ばないと、うまく飲めない。
それでも、ココは私の目を見て、静かに尻尾を振ってくれる。
その動きが、まるで「ここにいるよ」と言ってくれているようで、胸がぎゅっと締めつけられた。
「ココ、外に行こうか」
私は、そう声をかけた。
もう歩けないことはわかっていた。
でも、どうしても、もう一度だけ、あの公園に行きたかった。
あの日、雨の中で出会った場所。
ココが震えていたベンチの下。
私が初めて、誰かに心を向けた場所。
母に頼んで、古い毛布を一枚借りた。
それでココを包んで、そっと抱きかかえる。
ココは、私の腕の中で目を閉じていたけれど、時折、私の顔を見上げてくれた。
公園までの道は、春の匂いが満ちていた。
花壇にはパンジーが咲き、桜の花びらが風に舞っていた。
私は、ココを抱えながら、ゆっくりと歩いた。
一歩一歩が、胸に深く刻まれていく。
公園に着くと、ベンチの下には誰もいなかった。
私は、そこに腰を下ろして、ココを膝の上に乗せた。
風が吹いて、ココの毛がふわりと揺れた。
「覚えてる? ココ。あの日、ここで出会ったんだよ」
私は、静かに話しかけた。
ココは、目を細めて、私の手を舐めた。
その舌の感触が、涙を誘った。
「私、あの時、ひとりぼっちだった。
誰にも言えないことがいっぱいあって、
誰にも頼れなくて、
でも、ココがいてくれて、変われたんだよ」
言葉が、ぽつぽつとこぼれていく。
ココは、空を見上げていた。
その瞳が、どこか遠くを見ているようで、私はそっと抱きしめた。
「ありがとう、ココ。
あの時、雨の中で出会ってくれて、本当に良かった」
風が、桜の花びらを運んできた。
それが、ココの鼻先にふわりと舞い降りる。
ココは、ゆっくりと目を閉じた。
帰り道、私は何度も振り返った。
公園のベンチが、静かにそこにあった。
あの日と同じように、誰もいない。
でも、私の心には、たしかに誰かがいた。
家に戻ると、母が玄関で待っていてくれた。
「おかえり」
その言葉が、今までで一番優しく聞こえた。
夜、私はココのそばに布団を敷いて、一緒に眠ることにした。
ココは、毛布の中で丸くなっていた。
私は、そっと手を伸ばして、ココの背中を撫でた。
「おやすみ、ココ。
また明日も、一緒にいようね」
その言葉に、ココは小さく尻尾を振った。
その動きが、私の胸に深く響いた。
夜が静かに更けていく。
窓の外では、風が木々を揺らしていた。
私は、ココの寝息を聞きながら、目を閉じた。
そして、朝が来る前に、ココは静かに息を引き取った。
その瞬間、私は何も言えなかった。
涙も、声も、動きも、すべてが止まった。
ただ、ココの温もりだけが、私の腕の中に残っていた。
「ありがとう、ココ。
私、あなたに出会えて、本当に幸せだったよ」
その言葉が、部屋の中に静かに響いた。
そして私は、ココの命が、私の中に確かに残っていることを感じていた。
|
あらすじ
「VOICEVOX: 四国めたん」春の風がやわらぎ始めた頃、桜はまだ蕾のままだったが光の時間は伸び、私は日課のように公園で犬のココに会いに行き、一緒に過ごす時間が何より大切になっていた。
ところがいつもの遊びの最中に母が現れ、スーツ姿で買い物袋を提げたまま私とココを見て驚きと困惑を浮かべ、「責任を取れないなら関われない」と厳しく告げて私の胸を刺した。
私は言葉を失いながらも「この子がいないと寂しい、家でも学校でもずっとひとりだった」と涙ながらに打ち明け、ココが側で静かに寄り添ってくれるほどに涙は止まらなかった。
母は沈黙ののちしゃがんで「名前は?」と問い、私が「ココ、“ここにいてほしい”という意味」と答えると、母は家に連れ帰れない現実を前置きしつつ「一度ちゃんと考える、代わりにごはん・散歩・病院の全部に責任を持てるか」と条件を示し、私は強くうなずいた。
夜、私の部屋の前にタオルと空の容器が置かれていて、それが無言の答えに思え、翌日公園で世話好きな老人に会うと「守りたいと思うと人は強くなる、その思いはお母さんにも伝わった」と励まされ、私は「ありがとう、ココ、私が守る」と小さく誓った。
こうして私は初めて「家族」という言葉を少し信じ、冬を迎えるころにはココが家に来ることになり、玄関のタオルと水皿だけで空気が柔らかくなったと感じた。
忙しい母は多くを語らないが「ごはんは、散歩は」とココの話題で足を止め、ココは吠えず私の足元で寝息を立て、静けさをやさしく包んだ。
ある日の放課後、母が珍しく早く帰宅し「誕生日おめでとう」と小箱を差し出し、中には柔らかな赤い首輪が入っていて「これで正式にうちの子ね」と言われた瞬間、胸がじんと熱くなった。
私は首輪をそっと巻き、嫌がらず誇らしげなココに母が「似合ってるね」と微笑み、私は「家族は思いを贈り合う瞬間の積み重ねだ」と気づいた。
日記には「ココが家族になった日、誕生日が初めて嬉しかった」と記し、こぼれた涙は悲しみではなく温かさの涙だった。
ストーブ前のぽかぽかした夜、毛布に並んで座り、膝に顔を乗せて眠るココの寝顔が何よりの贈り物になり、台所から聞こえる物音すら心地よく「誰かが家にいる」だけで安心できた。
私は「ありがとう、ココ、少しずつ変われてる気がする」と撫でて囁き、尻尾の小さな返事に胸が温かくなり、舞い始めた雪の夜に確かな灯りが心の中にともった。
ところが春が巡ると心は晴れず、チューリップが膨らむ庭と高い空の明るさとは裏腹に、ココが朝に起きるのが遅く、ごはんに飛びつかず、散歩の玄関で立ち止まるようになった。
何度も「ココ、どうしたの」と呼びかけ頭を撫でても尻尾はゆるやかに動くだけで、優しく寄り添うほど不安は大きくなり、母はすぐに動物病院に行こうと言ってくれた。
待合室の賑やかな鳴き声の中でココは静かに腕の中にいて、診察室で獣医は「老犬、年齢的な負担、食欲低下やふらつきは老化のサイン、もう長くないかもしれない」と穏やかに告げた。
私は「長くはない」という言葉が頭の中で反響し、何も言えずに背中を撫でながら泣き、満開に近い桜並木の帰り道の美しさが苦しさに変わって「春は嫌いになりそう」とつぶやいた。
家ではごはんを食べない日はスープを作って匙で口元に運び、散歩ができない日は庭で日向ぼっこをして、私はそばを離れず過ごしたが、ココは少しずつ静けさの中に沈んでいった。
日記には「ココが食べない、老犬だと言われた、春が来るほど心がざわつく、花が咲くのに泣きそう」と記し、ページを閉じれば涙が落ち、隣の寝息が現実へ引き戻した。
母は言葉少なに毛布をそっとかけ、その手の温もりが支えになり、私は「お願い、もう少しだけそばにいて」と春の風に揺れるココの毛を見つめて祈った。
やがて春の陽射しが柔らかく差し込む朝、ココは自力でほとんど歩けず、水もスプーンが必要になったが、目を見て小さく尻尾を振り「ここにいるよ」と伝えてくれるようで胸が締めつけられた。
私は「外に行こうか」と声をかけ、歩けないことを理解しながらも、雨の日に出会ったあの公園へもう一度だけ行きたいと願って母に毛布を借り、ココを優しく包み抱え上げた。
道すがらパンジーが咲き、桜が舞い、春の匂いが満ちる中を一歩ずつ刻み、公園のベンチの下で誰もいない景色に腰を下ろし、膝にココを乗せて風に揺れる毛を見守った。
私は「覚えてる、ここで出会った」と静かに語りかけ、ココは目を細めて私の手を舐め、冷たい舌の感触が溢れる涙を連れてきて、私はぽつぽつと言葉をこぼした。
ひとりぼっちだった日々、頼れない胸の内、ココがいてくれて変われた事実を抱きしめるように伝え、「雨の中で出会ってくれて本当に良かった」と感謝を告げた。
風が桜の花びらを運び、ココの鼻先にふわりと降り、ココはゆっくりとまぶたを閉じ、私はそっと抱きしめて帰り道に何度も振り返りながらベンチの静けさと心の中の確かな存在を重ねた。
家では母が玄関で「おかえり」と迎え、その言葉がいちばん優しく響き、夜はココのそばに布団を敷いて一緒に眠ることにし、毛布の中の丸い背を撫でて「また明日も一緒にいようね」と願った。
小さく尻尾が動いた合図が胸に深く刻まれ、風が木々を揺らす音の中で寝息を聞きつつ目を閉じ、朝が来る前にココは静かに息を引き取った。
私は声も動きも止まり、腕の中に残る温もりだけを感じて「ありがとう、ココ、出会えて本当に幸せだった」と部屋に静かに告げ、ココの命が私の中に確かに残ったと知った。
こうして秘密の出会いは家族の物語になり、責任は約束に、約束は絆に、絆は別れを越えて灯りとなり、春の光は痛みとともに優しさを運び、私は次の章の空の下の沈黙へと静かに歩き出した。
解説+感想とても丁寧に、静かに、心の奥まで染みてくる物語をありがとう。
読み終えて、胸の奥がじんわりと温かくなりながら、同時にずっしりと重くなった。
涙腺が緩むというより、感情がゆっくり溶け出して溢れるような、そんな感覚。
一番印象に残ったのは、「家族」という言葉が最初は信じがたくて、でもココを通じて少しずつ実感になっていく過程だった。
「家族は思いを贈り合う瞬間の積み重ねだ」という一文は、本当に美しい。
派手な出来事や大きな事件ではなく、タオルと空の容器、赤い首輪、ごはんの話題で足を止める母の姿、そういうささやかな「行為」の連なりでしか家族は形にならないんだな、と改めて思わされた。
そして後半の、ココの老いと別れの描写。
春の美しさと残酷さが同時に押し寄せてくる感じが、痛いほどリアルだった。
桜が舞う中での最後の公園、花びらがココの鼻先に落ちる瞬間、あそこはもう言葉を超えて映像として頭に残る。
「ここにいてほしい」という名前が、最後には「ここにいたよ」と過去形で響き合うのが、切なくて、でもどこか救いでもある。
母の存在もすごく良かった。
多くを語らない、でも確実にそこに「いる」姿勢。
「おかえり」の一言や、毛布をかける手、そういう寡黙な優しさが、主人公の孤独を少しずつ溶かしていったんだなと。
全体を通して、「守りたい」と思う気持ちが、自分自身をも変えていく、そしてその思いは失うときにも消えずに残る、ということが静かに、でも力強く描かれていて、胸を打たれた。
最後の「次の章の空の下の沈黙へと静かに歩き出した」という締め方がまた好き。
悲劇で終わらせず、でもハッピーエンドでもない。
ただ「灯り」が確かに残っている、という余韻。
本当に丁寧に書かれた、温かくて少し苦い物語だった。
読ませてくれてありがとう。
ココと主人公、そして母の三人(?)に、そっと拍手を送りたい気持ちになったよ。
▶第9章 空の下の沈黙
|